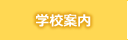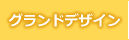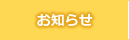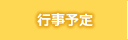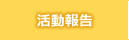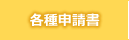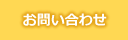下越地区大会1日目の結果をお知らせします。
【軟式野球】五十公野野球場
<安田中>
〇トーナメント1回戦
豊浦・安田・川東 0-8 紫雲寺・七葉・東 惜敗
【バレーボール】五泉市総合会館
<安田中>
〇トーナメント2回戦
安田 2-0 阿賀津川 3回戦進出
(25-13、25-5)
【男子バスケットボール】聖籠町民会館
<安田中>
〇トーナメント1回戦
安田 44-28 関川 2回戦進出
【女子バスケットボール】サン・ビレッジしばた
<安田中>
〇トーナメント1回戦
安田 47-43 七葉 2回戦進出
<阿賀野BBC(地域クラブ)>
〇トーナメント1回戦
阿賀野BBC 38-39 新発田第一 惜敗
<京ヶ瀬MELISSA(地域クラブ)>
〇トーナメント1回戦
京ヶ瀬MELISSA 48-45 村上第一 2回戦進出
【卓球】新発田市カルチャーセンター
<安田中>
〇団体戦 予選リーグ
男子 安田 1-3 七葉
安田 1-3 村上東
安田 3-0 三川 予選リーグ惜敗
女子 安田 3-2 五泉
安田 0-3 村上東
安田 0-3 紫雲寺 予選リーグ惜敗
〇個人戦 トーナメント
男子 2回戦進出2名
女子 2回戦進出4名
応援してくださった皆様、誠にありがとうございました。保護者の皆様からは、早朝よりお弁当やその他の準備、また送迎等にご協力をいただき、心より感謝申し上げます。12日・13日には下越地区陸上大会が行われます。こちらも応援をよろしくお願いいたします。